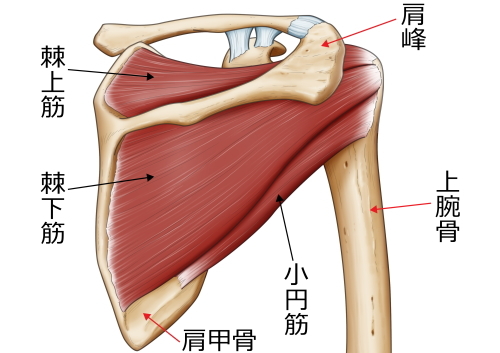- Tetsuya Hirasawa

- 2019年8月18日
- 読了時間: 2分
アップスフィットネスクラブをオープンして10ヶ月以上が経ち、また暑い季節がやってきました。暑い中、多くの会員様が熱心に通われ、しっかりとメニューをこなしていく姿を見て身が引き締まる思いです。どうしたら全員が健康になれるか?常に考えている生涯を掛けて行なうミッションですが、このミッションには「観察眼」が不可欠です。一人ひとり個性があるように身体つきや筋肉の付き具合、日ごろの動作の癖など同じ人は絶対に居ません。腰痛も10人いれば10通りの原因があります。つまりマニュアルがあれば何方でも対応できる という訳にはいかないのです。これはよくテレビでやっている「腰痛体操」「健康体操」などにも同じ事が言えます。その人の考え方、限界点の高さ、体力、動作の癖、筋肉のコンディションなどを考慮して指導して行かないと結果はでません。これは凄くハードルの高い事のように思えますが、クライアントとの距離が近い「小さいジム」ならば可能です。必ずご来店、退店時に挨拶する事ができます。そしてトレーナーはストレッチエリアの隣に駐在していますので、コンディションを目の当たりにする事が出来、じっくりと観察する事もできます。そのストレッチエリアで雑談を含みながら詳しくお話をする事も可能です。昔、大型店舗に勤めていた時、接客研修に行ってきたチーフが、「一流ホテルの接客」について熱弁していました。違和感を感じて聞き流していたのですが、この接客態度こそが、クライアントと溝を作り、話しづらくする原因だと思いました。つまり、気軽に話しかけられるトレーナーだけがクライアントを理解する事が出来、育てられるのです。
植木のように一鉢、一鉢、取り扱いに注意し、毎日様子を見ながら大切に育てていく、これが出来ない環境のジムは、決して人を健康に出来ないと思います。

※Ⅿ国大統領閣下と宮城県民様から、サボテン届きました。取り扱いに注意して大切に育てたいと思います(笑)